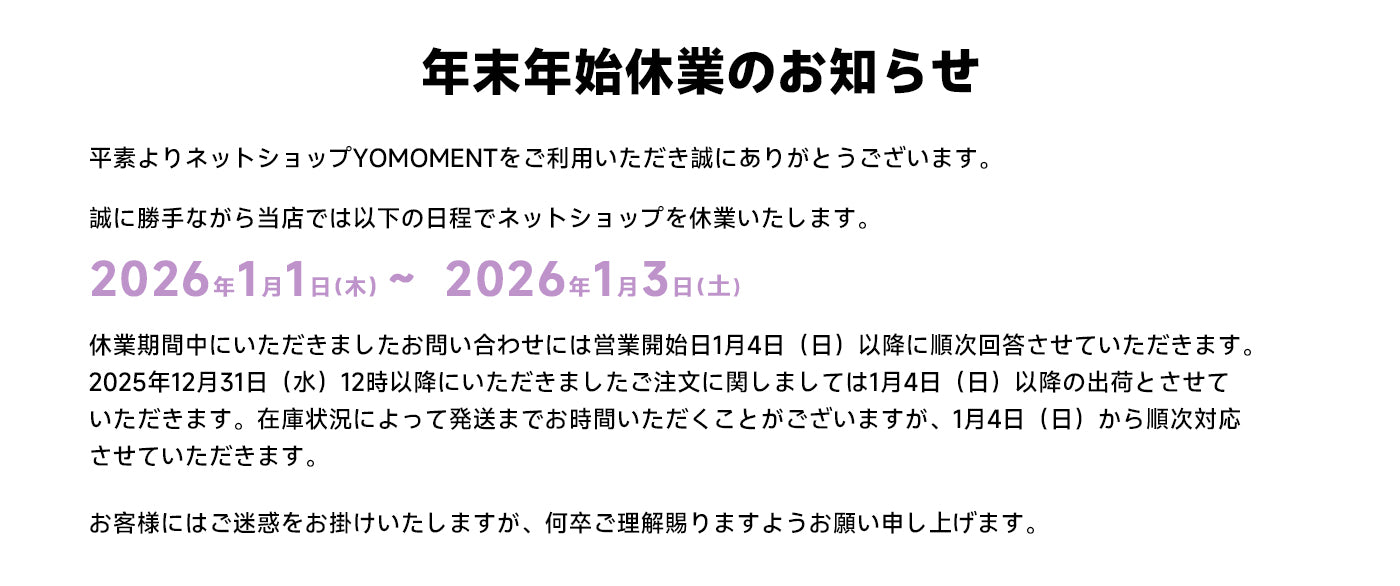News

【10月の服装】で悩まない!おすすめ秋コーデ&選び方のポイントも
夏から秋へ、大きく季節が変わる時期。
日中は汗ばむような陽気でも、朝晩は急に冷え込んだりと、1日の気温の変化が激しくなります。
また上旬から下旬にかけて、ひと月の気温の変化が大きいのも10月の特徴。
今回は、そんな気温の変化が大きい10月に悩みがちな服装についての特集です!
10月の時期によって変わる最適な服装を知って、秋ならではのファッションを楽しんでみてください。
______________________________________
薄手のトップスの重ね着で体温調節
秋めいてきたとはいえ、厚手の素材のアイテムではまだ少し暑いと感じる日も多いこの時期。
そんな時の服装は薄手のトップスの重ね着がおすすめです。その日の気温によって、半袖、長袖を上手に組み合わせてコーデしてみましょう。
昼夜の寒暖差に対応できる服装
朝晩の肌寒さが気になり始める10月上旬は、羽織ものが活躍します。
肌寒いと感じたらサッと羽織れる、カーディガンやストールなどを服装にプラスして。
レギンスのレイヤードコーデ
ロングスカートや長めのワンピースにレギンスを重ね履きすれば、今っぽい着こなしに。
レギンスと靴下の組み合わせもおしゃれで、防寒対策も兼ねた一石二鳥の履き方です。
定番のパーカーなら1枚で秋らしく
カジュアルアイテムのパーカーにチュールスカートなどを合わせれば、スポーティー×ガーリーのミックスコーデです。
ショート丈の明るい色を選べば、重たさを感じさせずにコーデが決まります。
秋らしい小物をポイントに
季節のおしゃれは小物からスタート。シンプルだけど存在感のあるものをセレクトすると洒落感や洗練度をUP。

薄着の季節、二の腕痩せするには?
上腕とも呼ばれる二の腕は、肩から肘までの部位のことです。
二の腕痩せをしたいと考えてはいるものの、食事や運動に気を付けてみてもなかなか細くならないと感じている方は多いでしょう。
二の腕の太さが気になってしまうと、夏場にノースリーブが着られなかったり、タイトなデザインの服を着たときに二の腕がパンパンでうまく着こなせないといった悩みにつながります。
【二の腕が太くなるのはなぜ?】
皮下脂肪が多い
特に、女性は男性よりも二の腕に限らず身体に皮下脂肪が蓄積されやすい傾向があります。これは女性ホルモンのエストロゲンが、皮下脂肪を蓄積する作用があるためです。
筋肉が使えていない
筋肉を使っておらず衰えてしまうと、その上を覆っている脂肪や皮膚もたるむ可能性があります。また筋肉を使わないと血流が悪くなるため、むくんだ結果、太くなっている場合もあるのです。
皮膚のたるみ
皮膚のたるみは、主に加齢によって生じます。腕に脂肪がついて体積そのものが増えているわけではなく、皮膚が伸びている状態です。
姿勢の悪さ
二の腕が太くなってしまうのは、姿勢の悪さも一つの原因です。
猫背などの背中が丸く曲がった状態は、肩甲骨が外側に開き、肩は内側へ向くため、肩回りや腕の筋肉が正しく使われなくなるので、二の腕や背中、肩回りに脂肪が蓄積しやすくなります。
また、姿勢が悪いと、脇の下に集中しているリンパの流れが悪くなり、むくみの原因となります。そこに脂肪が蓄積されると、さらにリンパの流れが悪くなるので、むくみと脂肪の悪循環が形成され、セルライトが形成されるのです。
【二の腕痩せのためにはどうすればいい?】
食事制限で摂取カロリーを控え、運動で消費カロリーを増やす基本的なダイエットによって、二の腕痩せは可能です。
脂肪を燃焼させるには、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動が効果的です。
二の腕のむくみやセルライト対策にも筋トレは効果が見込めます。二の腕の筋トレを行うことで、血液やリンパの流れを促進し老廃物を排出しやすくなるためです。
二の腕マッサージ
鎖骨の中心あたりから脇に向かってリンパを流すように手のひら全体で優しく押し、わきの下のリンパ節を強めに5秒ほど押します。
親指と人差し指の骨が交わる「合谷(ごうこく)」というツボを、親指で15~20回ほど押圧します。
手首を手のひらで包み込むように握り、肘に向かって優しくさすりながらマッサージします。
肘の内側の横線から指3本分の位置にある「手三里(てさんり)」というツボを親指で押します。
肘から肩にかけて、手のひら全体で包み込むようにしっかりとマッサージし、リンパの流れを促します。
再度1を行った後、反対側も同様に1~6まで行います。
ダンベルキックバックのやり方
ダンベルを用いたキックバックの実施方法ですが、左手でウエイトを持ち上げる場合で説明します。
ベンチなどに右手と右膝をつき、左腕は上腕が地面と水平に、前腕が垂直になるように構えます。この状態から肘を伸ばして左腕全体が地面と水平になるまでウエイトを上げていきます。この時脇は開きすぎず、ダンベルが体に当たらないくらいに自然に腕を下ろしていきます。
キックバックの動作は肘関節の伸展と呼ばれ、肘関節のみが動作する単関節運動です。
したがってできるだけ肘の位置が動かないようにしましょう。前後に肘が動いてしまうと負荷が肩や体幹に逃げてしまい、トレーニングの効果が下がってしまいます。
リバースプランク
この運動は肩の位置を整えながら、二の腕の筋肉を使うことができるトレーニングです。猫背姿勢や巻き肩を改善するためにも効果的なトレーニングです。
⒈体育座りで座り、手をお尻の後ろに移動します。指先はお尻の方を向け、手の平一枚分お尻から遠ざけます。
⒉足の幅は拳1個分を保ち、骨盤を自分の方へ傾けます。
⒊ゆっくりとお尻を持ち上げ、肩から膝まで一直線になるようキープしましょう。
ベンチディップス
後ろ手にイスやテーブルなどのの縁をつかむ
軽く膝を曲げた状態で足をイスから50cmほど離す
出来る限り足の力は使わずに肘を伸ばして体を持ち上げる
肘を曲げてゆっくりと体を下ろす
15回繰り返す

夏にうれしい機能性が充実!楽ちん軽やかボトム特集
足元も軽やかにアクティブな季節を楽しみたいところ!
暑い日でも快適に過ごせるさわやかボトムは夏に欠かせないアイテムです。
サラッと軽い履き心地のワイドパンツや、触るとひんやり感のある冷感素材のカジュアルパンツなど、
夏にぴったりなボトムをご紹介します♪ぜひチェックしてみてください!
——————————————————————————————————————
夏の人気アイテム。さらさらとした涼しげな履き心地、サイドには便利なポケット付き、ウエストはゴム仕様で窮屈感がなく、
今年も長く暑い夏に様々なシーンに合う、スマートなデザイン。
カジュアルすぎない綺麗なシルエットのワイドパンツ、夏のコーデに洗練された印象をプラス。
さらっとした軽い履き心地、すっきり美脚を叶えます。
裾に向かって広がるフレアなシルエットで、脚長効果も期待出来るレギンス。
十分にストレッチが効いているので動きやすく履き心地抜群◎
どんなアイテムとも合わせやすいから、幅広く活躍してくれそう。
1点投入するだけで、こなれ感溢れるスタイリングに。
ふんわりとしたシルエット、ラフな穿き心地に仕上げたミニスカート。
インパン付きで安心感もあり、普段使いしやすく、アクティブなシーンにもマッチ。
吸湿速乾機能があり、ストレッチも効いて動きやすく履きやすいレギンス。
合わせ方でデイリーウェアとしても活躍しそう、シーンレスな定番アイテムです。

ハミ肉をスッキリさせて美背中を目指そう!「背中痩せ」を叶えるヨガポーズ
夏本番!そろそろ背中のたるみが気になる季節ではないでしょうか?
ふと鏡を見たときに、下着からはみ出た背中の肉に、がっくりと肩を落としたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。
背中に肉が付いていると、夏場にプールなどで水着になりたくても二の足を踏んでしまったり、友人やパートナーと温泉旅行に行くことに抵抗を感じてしまったりすることもあるはず。
「では、一体なにをすればスッキリとした後ろ姿が手に入るの? 」
________________________________________________________________________________________________
背中に肉が付く原因
背中にお肉がつくのは、主に猫背・姿勢が悪い・加齢・運動不足・脂肪量が多いが影響しています。
猫背や運動不足の方は背中の筋力が低下してゆるみ、脂肪がつきやすくなるのです。
単純に体全体の脂肪量が多いという理由で、背中に肉が付いている場合もあります。
姿勢が悪いとさまざまな部位に脂肪が付きやすくなってしまいますが、背中にも肉が付きやすくなります。
デスクワークやスマホを見る時間が長い方、座る時に浅く腰掛けて背もたれを利用する方などは要注意です。
また加齢で代謝が落ち、昔は気にならなかった箇所に脂肪がつくのも珍しいことではありません。
背中痩せヨガで背中の筋肉を刺激することで、肩甲骨回りがほぐれます。
背中の血行も促進され、代謝が上がって痩せやすくなるんです◎
筋トレやエクササイズが苦手な方も気軽に取り組めるので、ぜひ実践してみましょう!
①:コブラのポーズ
うつ伏せの状態から、両手を胸の横に置きます。
息を吸いながら、同時に両手で床を押し、上半身を起こしていきます。胸を天井に向けるようにし、目線は斜め上に向けます。肩甲骨を寄せてキープをし、吐きながらゆっくり戻ります。
腕で押して腰が反るだけにならないように、背中の筋肉をしっかり使うように意識しましょう。
②:バッタのポーズ
うつ伏せの状態で、額は床につけます。
両腕は体側に沿って手のひらを上向きに置きます。軸となるお尻は締めて、下腹部や骨盤は床につけたまま、息を吐きながら頭・上半身・両腕・両脚を床から離していきます。
両腕は床と並行を意識し、指先も伸ばします。肩に力が入らないように意識し、背面の筋肉を収縮させます。
③ラクダのポーズ
両ひざで立った状態から、両手を腰に当てます。胸を開きながら、上半身を少しずつ後方に反らせます。
ゆっくり右手で右のかかとを、左手で左のかかとをつかみ、胸は天井に向けていきます。
この状態をキープし、ゆっくり元の位置に戻ります。
呼吸を整えて、同じ手順で繰り返していきます。
④太鼓橋のポーズ
仰向けになり足を腰幅ほどに開く
手は体の脇に自然に伸ばす
かかとをお尻にできるだけ近づけるように、膝を立てる
息を吸いながら腰を持ち上げる
両手を腰の辺りで組み、肩甲骨を寄せる
⑤リバースプランク
床に座り、脚をまっすぐ前に伸ばす。
両手を肩の少し後ろにつき、指先は足の方向に向ける。
肩甲骨を寄せながら胸を開き、ゆっくり息を吐きながらお尻を持ち上げる。
頭からかかとまでが一直線になるよう意識し、15~30秒キープ。
ゆっくりお尻を床に戻す。
⑥バックエクステンション
床にうつ伏せになり、脚を腰幅に開く。
両手を頭の後ろで組むか、腕を前に伸ばす。
息を吸いながら、背中の筋肉を使って上半身を持ち上げる。
目線を斜め前に向ける。
※首が反りすぎないように注意。
息を吐きながら、ゆっくり元の姿勢に戻す。
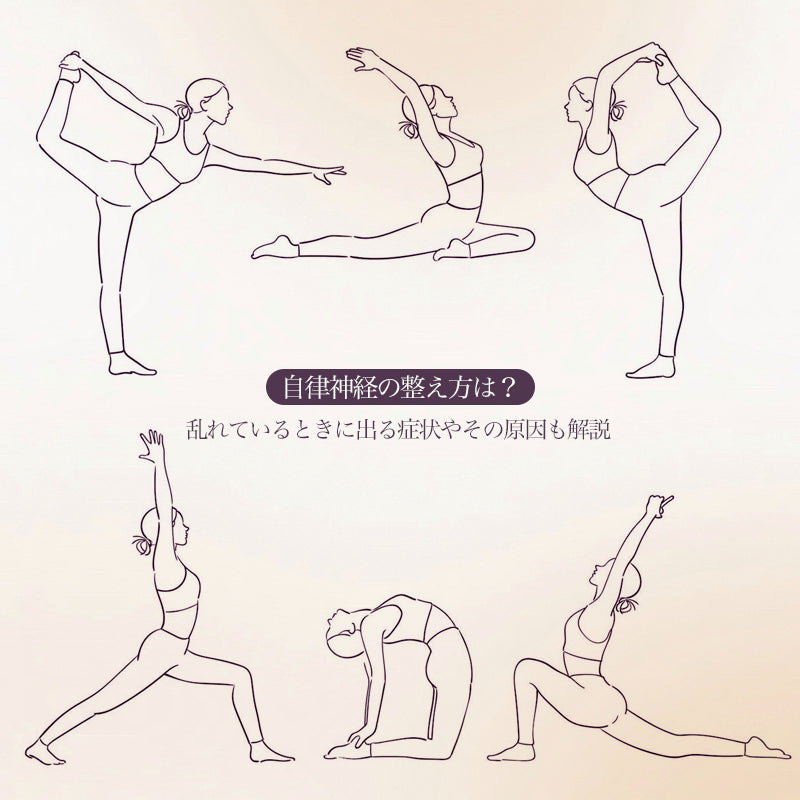
自律神経の整え方は?乱れているときに出る症状やその原因も解説
私たちの身体は、外の環境や身体の内側に変化が起きても、生命維持に必要な生理的な機能を正常に保とうとする働き(恒常性)があります。
その重要な役割を担っているのが自律神経で、正常に働かないと身体に不調をきたします。
この記事では、自律神経の働きについて解説し、自律神経が乱れることで現れる症状と原因、自律神経を整える方法も紹介します。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
自律神経は交感神経と副交感神経の2つからなり、自分の意思では動かせず、無意識に働く神経を指します。
自律神経には、交感神経と副交感神経がバランスを取り合い、外部からの刺激や体内の変化に反応して内臓や血管などの機能をコントロールする役割があります。
交感神経は、一般的には、身体を動かしたときや緊張したとき、ストレスを感じたときに活発化します。
副交感神経は主にリラックスしているときや眠っているときに優位になります。心拍数や血圧を低下させることにより身体の回復やエネルギーの補給をうながしたり、消化管の働きを活発化させて消化や排せつをスムーズにおこなったりする役割を担っています。
しかし、自律神経が乱れると交感神経と副交感神経のバランスが崩れ、心身の不調をきたす場合があります。
あなたの自律神経は大丈夫? チェックリストで確認しよう
● 寝つきが悪く、夜中に何度も目が覚めたり、朝早く目が覚めたりする
● 疲れや身体のだるさを感じることが多い
● 頭痛やめまい、立ちくらみが起こりやすい
● 急な胸の苦しさや、息苦しさを感じることがある
● 不安やイライラが持続している
● ささいなことに神経質になる
● 落ち着かずそわそわしてしまう
● 動悸や胃もたれ、胸やけが頻繁に起こる
● 便秘や下痢が続いている
● 手足の冷え、しびれ、慢性的な肩こり、腰痛、耳鳴りがある
● 風邪を引きやすく、体調不良が続きやすい
● 目が疲れやすい
●発汗の異常
● 食欲不振や体重減少がある
自律神経が乱れる原因
生活習慣の乱れ
不規則な生活リズム、睡眠不足、運動不足などは自律神経が乱れる原因になり得ます。
精神的、身体的なストレス
ストレスは不安・緊張・心拍数が上がるなど、交感神経が優位になります。ストレスが長期間続くと、通常なら副交感神経優位の休息モードに入るはずの時間帯も交感神経優位の活動モードが続き、自律神経のバランスが崩れた状態になります。
季節の変化
季節の変わり目には、気温や気圧の急激な変化などに自律神経が適応しようと過剰に働くことでバランスが乱れやすくなります。
ホルモンバランスの乱れ
女性の月経周期、妊娠中、更年期などはホルモンの変動が大きく、自律神経のバランスが崩れやすいです。男性では加齢によるホルモンバランスの変化が自律神経に影響する場合があります。
自律神経を整える方法
生活リズムを整える、十分な睡眠を確保する
十分な睡眠は、自律神経を整える効果が期待できます。早く寝ることを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。
適度な運動に取り組む
適度な運動は、副交感神経の働きを高めます。1回30分程度のウォーキングや階段による移動、すきま時間のストレッチや筋トレなどに取り組むとよいでしょう。ただし、負荷が大きすぎる運動は自律神経の乱れにつながる可能性があります。
食生活を改善する
1日3回の規則正しい食事は、自律神経を整えるためには大切なことです。栄養バランスのとれた食事は、自律神経が乱れるリスクの低減につながるとされています。
マッサージを行う
マッサージで身体がリラックスし、筋肉の緊張やこりが改善され、血行が良くなるとともに、副交感神経優位な状態に切り替わります。場所を取らず、気になったときにその場でできる、耳や目の周りのマッサージも効果的です。

冷房で体が冷えすぎる…何か対策はないの?
夏場の冷房は有り難いですが、ずっとついていると逆に寒くなってきてしまいますよね。
暑さ対策だけでなく、冷房対策もお悩みのひとつではないでしょうか。
暑くて冷たいものを飲みすぎたり、冷房で身体を冷やしすぎたりして、こんな不調に見舞われた経験はありませんか?
・胃もたれや消化不良、下痢、便秘などにつながりやすい
・暑い屋外と寒い室内の出入りを繰り返すと、体温調節の役目を持つ自律神経が乱れやすい
・夏バテっぽい
冷房で体を冷やし過ぎない対策をしよう!
寒くなったらカーディガンを着る
ショッピングモールやオフィス、電車など、夏であってもさまざまな場所で冷房が効きすぎて寒さを感じることがありますよね。
暑〜い外から一歩屋内に入った瞬間、冷たい空気に思わずブルッ!
特に商業施設や公共交通機関などでは、冷房の温度を自分で調整できないため、対策が必要になります。
カーディガンやジャケットなどの羽織物を常備しておくのがおすすめです。
冷えを感じたときにすぐ羽織れるため、温度調節に役立ちます。
吸汗速乾インナーで汗冷えを防ぐ
吸汗速乾インナーを着用しておくと、汗をかいても肌の温度が下がる前に汗を吸収・乾燥させ、汗冷えを防ぐことができます。
下半身をあたためる
「冷房による冷たい空気は下にたまりやすい性質があります。
外的な冷えから下半身を守るため、下半身をあたためるためにひざ掛けが一般的ですが、レッグウォーマーで脚全体をあたためるのも効果的です。
常温か温かい飲み物を摂取する
冷えたものは体の熱を奪ってしまうので要注意。
夏なので水分補給は大切ですが、キンキンに冷えたものではなく、できるだけ常温か温かい飲み物を選びましょう。紅茶やウーロン茶、しょうが湯などは体を温める効果があるのでおすすめです。
定期的にストレッチや運動をする
長時間同じ姿勢をとっていると血行が悪くなり、冷えを感じる原因になります。また、筋肉量が少ないと熱の生産量も少なくなり、冷えやすくなってしまうので注意が必要です。
定期的に肩や腰を軽く伸ばしたり、できるだけ移動するときは階段を利用したりするのと良いでしょう。
寒いジムは服装で対策
夏の暑さが厳しくなると、屋外での運動が難しくなります。
室内での運動でも汗をかきますので、 通気性の良い素材や吸湿速乾性のあるウェアを選ぶことで、快適に運動できます。
薄手の長袖にする、インナーにタンクトップ などで冷房対策になります。

日焼けをしたあとはアフターケアが大事!早めにやっておくべきケア方法とは
紫外線はお肌の大敵――。そう分かっていても、毎日日焼け止めを塗るのが面倒で、ちょっとしたお出かけなら大丈夫だろうとおもって、うっかり日焼けしてしまうことはありますよね。
日焼けを放置しておくと、肌に炎症が起こったり、シミやしわ、くすみといった将来の肌トラブルにもつながるため、日焼けをした際にはアフターケアが必要です。ここではそのケア方法をご紹介します。
_________________________________________
日焼けとは軽いやけどの状態
日焼けには2段階あります。紫外線を浴びた直後から起こる赤くなる日焼け「サンバーン」と、数日後に黒くなる日焼け「サンタン」です。
特にサンバーンは、紫外線による肌の「やけど」といっても過言ではありません。肌の細胞内の遺伝子が傷ついたり、炎症が起きたり、その結果として皮膚細胞が死んでしまったりと、緊急事態が起きているのです。
ほてり・赤み・ヒリヒリ痛むこともある
赤くなる日焼け「サンバーン」の症状は、紫外線を浴びてから最短4時間ほどで始まり、8~24時間前後でピークをむかえ、2、3日後には次第におさまっていきます。サンバーンにともなう痛みのピークは、紫外線を浴びてから6~48時間ほどだといわれています。
一方、紫外線を浴びてから72時間(3日)以降は、メラニン色素をつくる色素細胞(メラノサイト)が活性化し、メラニンの生成が始まります。その結果が黒くなる日焼け「サンタン」です。これは本来、次に紫外線を浴びたときに肌を守れるよう備えるための防御機構なのですが、メラニンの過剰生成は将来の肌トラブルの原因にもなります。
なお、ひどい日焼けの場合、3~8日以降になると死んだ皮膚細胞が剥がれ落ち、皮むけが起こります。
日焼け後のケアを怠れば将来的な肌トラブルの原因になることも
サンバーンやサンタンといった日焼けは、シミなどの原因としては認識されますが、実は日焼けを長年しつづけることで皮膚内の細胞組織に少しずつダメージを与えるため、そのシーズンの問題にとどまらず、将来的な肌トラブルにつながります。実際のところ肌のシミ、しわ、たるみといった「肌の老化」の80%は、紫外線のダメージのせいだともいわれており、この現象は「光老化」(ひかりろうか)とも呼ばれています。
加齢による老化が経年で起こるのに対し、光老化の進み具合は浴びた紫外線の量や強さ、時間などで決まります。つまり、肌の老化を遅らせるためには、日々の紫外線対策の積み重ねが大切で、常に紫外線防御と日焼けのアフターケアを行うことが肌の老化を防ぐ決め手となるのです。
光老化では、紫外線を多く浴びたパーツに次のような症状がみられます。
・シミ
・そばかす
・深いしわ
・乾燥と肌あれ
・弾力性の減少
日焼けをした肌のアフターケア方法
【直後】冷やす
日焼けをした皮膚は炎症を起こしているので、和らげるためにその部分を冷やすことは効果的。
火傷したときと同様に流水をしばらく当てるようにすると炎症が和らぐ。
凍らせた保冷剤や氷などで冷やす場合はタオルなどで包み、患部に直接あてないようにしよう。
かゆみや痛みの程度が弱いなど自覚症状がないときは、まずは経過観察してもOK。
肌が冷えたらしっかりと保湿する
肌のほてりや赤み、痛みが引いてきたら、皮膚を保湿して保護しましょう。
日焼け後の肌は紫外線によって角質層がダメージを受け、バリア機能が低下しているため、表面の水分を補ったり、外部からの刺激から肌を守ったりするために保湿をすることで肌を保護してあげる必要があります。
日焼け直後の肌は敏感になっているので、保湿の際も注意が必要です。
化粧水をつけるときは強くパッティングせず、やさしくプレスするようにしましょう。また、日焼けがひどく肌に炎症が起こっているときは、日頃のスキンケア商品の使用は中止し、肌の状態が改善したあとに乾燥肌や敏感肌にも使いやすい低刺激性のものを選んで保湿しましょう。
水分やビタミン補給も大切
日焼けしたあとの身体は、水分が失われてカラカラの状態です。そのため、積極的に水を飲み、身体の内側から水分補給してあげることも欠かせません。
さらに日焼け後は、肌の修復のために必要な栄養素も普段より多く消費されます。特に、以下の成分を意識して補給しましょう。
・ビタミンC:しみの原因となるメラニン色素の定着を抑え、コラーゲンの合成を助けます。酸味のある果物や葉野菜などに多く含まれています。
・ビタミンE:血行を促進し、肌のはりやターンオーバーを整えます。ナッツ類や大豆製品などに多く含まれています。
【落ち着いたあと】シミ対策
紫外線対策の基本は日傘や帽子、日焼け止めクリームを使用すること。
「冬は紫外線が少ないから、特別なケアはいらないかな」「朝と夕方しか外を歩かないから、紫外線は浴びてないはず……」と考える方もいます。
しかし、紫外線は1年を通して肌にダメージを与えています。
天候に関係なく、できる限り日焼け対策をすることでシミの悪化を予防できる。
また、日常生活ではストレスをなくすように心がけよう。
紫外線に打ち勝つにはバランスのいい食事を心がけ、ビタミン豊富な野菜や便秘予防のための食物繊維などを積極的にとって、健康的な肌を保つことも大切に。

【接触冷感】涼やかアイテム特集
暑い日がまだまだ続く長い夏は、涼やかアイテムで快適に過ごしたいですね!
今回は触るとひんやり感のある接触冷感素材や、見た目も涼やかなアイテムをご紹介します。
ぜひチェックしてみてください。
————————————————————————————————————————
冷感タッチの素材と立体感あるシルエット、夏の一枚着にちょうどいい厚さです。
バックデザインもポイント。
とにかくムレる、谷間やワイヤー部分に汗がたまるなど、夏になると起こりがちな胸もとの不快感やトラブル。
涼しげな服が増えてきたら、ブラジャーの衣替え、してる?夏には「夏ブラ」で心地いい毎日へ!
伸縮性があり着心地のいい素材にひんやりとした冷感機能をプラスしたカジュアルパンツ。
蒸し暑い日も快適に過ごせるのが◎
様々なシーンで活躍する夏に履きたいパンツです。
コーデのポイントになる夏らしいカラーのパーカは薄手で軽やかな素材だから季節の変わり目に持ち歩いても邪魔になりません。
またUVカット機能がついており、日常に心地よく寄り添ってくれる優秀アイテムです。
シンプルなノースリなら程よくカジュアル、ヘルシーな肌見せがか叶えます。
通気性がよく動きやすい、アクティブなシーンでも活躍できるアイテムです。

〈カラーアイテム〉夏本番に向けて差し色を買い足そう!
ふだん白や黒などベーシックカラーのお洋服を身につけているモノトーン派さんも、
セールのときこそカラーアイテムに挑戦してみませんか?
お得に買えるときこそ狙い目ですよ◎
夏に纏いたくなるアイテムを色別にピックアップしました。
気になるカラーをぜひ取り入れてみてください!
——————————————————————————————————————
清涼感あふれる〈ブルー・グリーン〉
涼やかなブルー・グリーンを身に纏えば、暑い夏も爽やかに過ごせそう。
ホワイト系のお洋服を重ねたりするのもいいですね。
ロマンティクで女性らしい〈ピンク・パープル〉
女性らしい印象をプラスしてくれるピンクやパープルは、ぜひセールでゲットしたいときめきカラー。
淡いトーンの色を選べば、いつものコーデにもさらっと取り入れられますよ。
トレンドのアースカラー〈ブラウン・カーキ〉
カラーアイテムがちょっぴり恥ずかしい…という方は、落ち着いたトーンのブラウンやカーキから取り入れてみませんか?
特にブラウンは今年のトレンドカラー。今まさに注目の色!
コーデに取り入れるだけで、リッチで柔らかな印象に。
ハッピーな気持ちになれる〈イエロー・レッド〉
夏の装いに映えるイエローやレッドは、気持ちもハッピーになれるビタミンカラー。
さらっと羽織にしたり、一枚で着たりするのもおしゃれ。
マンネリコーデを打破してくれるとっておきのアイテムです。